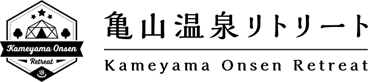亀山湖の渡り鳥
【2025年2月17日ブログ掲載】

茶枯れた冬枯れの道端を覗き込んだら、落ち葉の下には春の新芽が出てきています。
天気予報によると今夜から寒気が流れ込んできて、気温が下がる予想ですが、こうして自然と共に生きていると、その先にやってくる春を、私は確実に感じ取っています。

さて、今週末から今月末にかけてレイクリトリートプランや広域ネイチャーガイド、とある企業さんのリトリート事業開発の視察対応など、様々な方がリトリート体験にいらっしゃいます。
それらの体験に向けて、今の亀山湖の様子を下見してきました。
リトリートの分野には様々な業態が生まれていて、精神性を重視したスピリチュアルなツアーを開催するところ、断食道場をベースにしたところや、エビデンス(科学的根拠)を重視した医療的なところもあります。
そんな多様性のなかで、こちらは自然体験型リトリートとしてアウトドアを基調としたプログラムを実施しています。
視察にいらっしゃる企業さんは医療的な事業の開発を予定されているそうですが、この時期の自然体験は何といっても「渡り鳥の観察」ここはひとつ、医療関係の方もバードウォッチングにご案内して、野鳥観察が心身に与える医学的効能を調べてもらいたいと思います(笑)

さて、冬の亀山湖、水面を見ると多くの鴨(カモ)が羽を休めています。
実はこの鴨たち、その多くが渡り鳥で春になると大陸(主にユーラシア大陸)に戻ってしまいます。
残るのは、ある意味「日本人(日本鴨?)」とも言えるカルガモくらいになります。

こちらがカルガモ、日本全国の田んぼや公園にいっぱいる鴨で一番よく見かける種類です。
田んぼの用水路や、海近くの運河、都市に流れる小さな川まで「こんなところにもいるの?」と思うくらいタフで、水草から雑草の新芽などの植物性の物、カニやエビ、ミミズなどの動物性のものなど何でも食べる雑食性の鴨です。

全国、どこに行っても水場があればカルガモはいます。

全国、どこに行っても田んぼがあればカルガモはいます。泥に顔を突っ込んで雑草の新芽やら種、ミミズや蟹やエビに至るまで何でも食べます。

よく、カルガモの親子が道路を横断する様子などがニュースに流れたりしますが、他の種類の鴨たちは地元の大陸に戻って子育てしているため、他の鴨の子育ての様子は日本では見られないからです。

さて!前置きはさておき、何が言いたいかといいますと、この時期は渡り鳥としてやってくるいろんな種類の鴨が亀山湖には、たくさんいるということです。

こちらはマガモ、オスはアオクビと呼ばれ首が青いのが特徴です。
亀山湖には意外と少なく、どちらかというと公園の池など水深の浅い水場にいることが多いです。

なぜかというと、マガモは深く潜れないからですね、こうして潜るというより「首を突っ込む」くらいのことしか出来ません、何かカワイイ(笑)まさに頭隠して尻隠さずです。

これはカルガモも同じです、頭を突っ込んで底を突っつけるくらいの水深にいることが多いです、だから田んぼや小川、公園の池などになどにマガモやカルガモは多いのですね。
先日、隣の鴨川市の別荘オーナーから別荘の有効活用についての相談を受け、話を聞きに行きました。
隣にため池があって、そこにはマガモとカルガモがいっぱいいたのを覚えています、亀山湖からは直線距離で10キロくらいしか離れていませんが、ちゃんと飛んでくる場所も種類によって違うんだなと自然界の

さて、田んぼや公園の池と違って水深の深い亀山湖は、飛んでくる鴨の種類も少し違います。
こちらはホシハジロ、鴨ですが「ハジロ属」と呼ばれる羽に白いラインが入っている種類です。
ハジロ属は、とても潜水が上手で深く潜っては小魚や蟹やエビなどの生き物を捕食しています。

こちらはキンクロハジロ、私が見ている限り一番潜水時間が長いように思います。
クチボソ(正式名称はモツゴ)と呼ばれる、釣りの対象にならない小さい小さい小魚を捕食することが多いです。
同じところに棲み付く傾向があるようで、冬場は通勤の時に「今日もいるかな、、」とこのキンクロちゃんの存在を確認するのが密かな楽しみでもあります。
春になって居なくなっていると、一抹の寂しさを感じてしまいます、大陸に戻って行ったんだな、と。
先日、隣の鴨川市の別荘オーナーから別荘の有効活用についての相談を受け、話を聞きに行きました。
隣にため池があって、そこにはマガモとカルガモがいっぱいいたのを覚えています、亀山湖からは直線距離で10キロくらいしか離れていませんが、ちゃんと飛んでくる場所も種類によって違うんだなと自然界の動物たちの知恵に関心してしまいます。

さて、こちらは「オオバン」鴨そっくりですが、少し種類が違います。
頭をクイクイと鳩のように動かしながら進むのが特徴です。
いつもパクパクと水草や草の新芽などを突っついていて、カルガモに似てとても繁殖力の強い個体です。
今は、どこに湖沼に行っても、また運河など海に近いエリアでも「ここにもいる!!」と、オオバンを見かけます。きっと全国的にこのオオバンが増えているのだと思います。
潜り方も上手で水深の深い亀山湖にもいるし、カルガモ並みに何でも食べて浅い用水路にもいますし、こういう「二刀流」の生き方をしている動物は、どんな場所でも生息し、環境の変化にも対応しているように思います。
そんなことを感じながら、亀山湖を下見してきました。